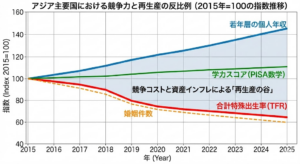寺院側の「ビジネス化」と檀家制度の崩壊
一方で、この問題を「葬儀社=悪、寺院=被害者」という単純な図式で語ることもまた、公平ではありません。筆者が大学時代に見聞きした現実には、生き残りのために「聖域なきビジネス化」へ舵を切る寺院の姿もありました。
檀家離れが進む中、一部の寺院は檀家の年収や社会的地位をリサーチし、ターゲットを絞って高額な寄付や仏具を提案するマーケティング手法を取り入れていました。また、資産価値の高い境内地を利用して不動産ディベロッパーと結託し、マンション経営や投資商品としての永代供養墓販売に傾倒するケースも散見されました。 伝統的な「信頼関係」を維持できず、こうしたビジネス的なアプローチに走らざるを得なかった寺院側の姿勢もまた、現在の「仲介業者依存」を招いた一因と言えるでしょう。
プラットフォーマーによる「死の商流」独占
なぜ75%もの手数料がまかり通るのか。その最大の要因は、葬儀社が「顧客接点(ラストワンマイル)」を完全に独占したことにあります。
現代の都市生活者にとって、死が発生した際の最初の連絡先は「菩提寺」ではなく、スマホ検索で見つけた「葬儀社」です。ビジネスにおいて、最初の入り口を握る者が価格決定権を持ちます。 葬儀社は、寺を持たない遺族と、仕事が欲しい僧侶をつなぐ巨大なマッチング・プラットフォームと化しました。そこでは僧侶は「代替可能なコンテンツ」として扱われ、低賃金での労働(読経)を余儀なくされる「ギグワーカー化」が進行しています。
「死の値段」を誰が決めるのか
本来、お布施とは「定価のない寄付」であり、感謝の対価でした。しかし、葬儀社が価格表を作り、手数料を上乗せした時点で、それは「サービス料金」へと変質しました。 消費者は「お布施」として払っているつもりが、実際にはその大半が広告費や仲介手数料に消えている。この「情報の非対称性」こそが、今回問われている「死の値段」の不透明さの正体です。 「死の値段」が、信仰や感謝ではなく、プラットフォームの維持費によって決定されている。この現実に、私たちはどう向き合うべきでしょうか。
実効性のある解決策:テクノロジーと「ライトな縁」の再構築
では、私たちはどうすればこの構造から抜け出し、納得のいく送り方ができるのでしょうか。「生前に寺と仲良くしましょう」という精神論だけでは、現代社会では機能しません。より具体的で実効性のある3つのアプローチを提案します。
1.「寺院版D2C(Direct to Consumer)」の活用
葬儀社という「中抜き」を排除する仕組みを使うことです。 現在は、僧侶と利用者を直接つなぐ透明性の高いマッチングアプリやウェブサービスが登場しつつあります。そこでは僧侶のプロフィール、法話の動画、実際の利用者のレビューが可視化されており、手数料も適正です。 Amazonで生産者から野菜を直接買うように、消費者自身がテクノロジーを使って僧侶を直接指名する。これが最も即効性のある自衛策です。
2.「サードプレイス」としての寺院利用
いきなり「檀家」になるのはハードルが高いですが、寺院を「カフェ」や「コワーキングスペース」、「ヨガ教室」として開放している場所が増えています。 宗教的な契約ではなく、まずは「場所」の利用者として寺に出入りしてみる。住職の人柄を知る機会があれば、万が一の際も「あのご住職にお願いしたい」と直接依頼ができます。これは、葬儀社を介さない自然な「指名ルート」の確保になります。
3.「サブスク型」のライトな檀家制度(会員制度)
高額な寄付や義務を伴う従来の檀家制度ではなく、月額数百円〜千円程度で寺院をサポートする「会員制度(サポーターズクラブ)」を導入する寺が増えています。 見返りは「悩み相談」や「ニュースレター」程度ですが、これにより「会員価格」で葬儀や法要を直接依頼できる契約を結べます。 消費者にとっては安価な保険となり、寺にとっては安定収入となる。互いに負担の少ない、現代版の「縁」の結び方です。
結論
75%の手数料問題は、私たちが「死」の手続きを思考停止して業者に丸投げしてきた結果の産物でもあります。 「死の値段」は、ブラックボックスの中で業者が勝手に決めるものではありません。それは本来、送る側と送られる側、そして弔う側(僧侶)との間の、透明な関係性の中で決まるべきものです。
テクノロジーを活用して中抜きを回避する賢さと、少しだけ寺院という場所に足を踏み入れてみる行動力。その小さな一歩が、故人を送る最後の大切な時間を、商業的な搾取から取り戻す唯一の方法ではないでしょうか。